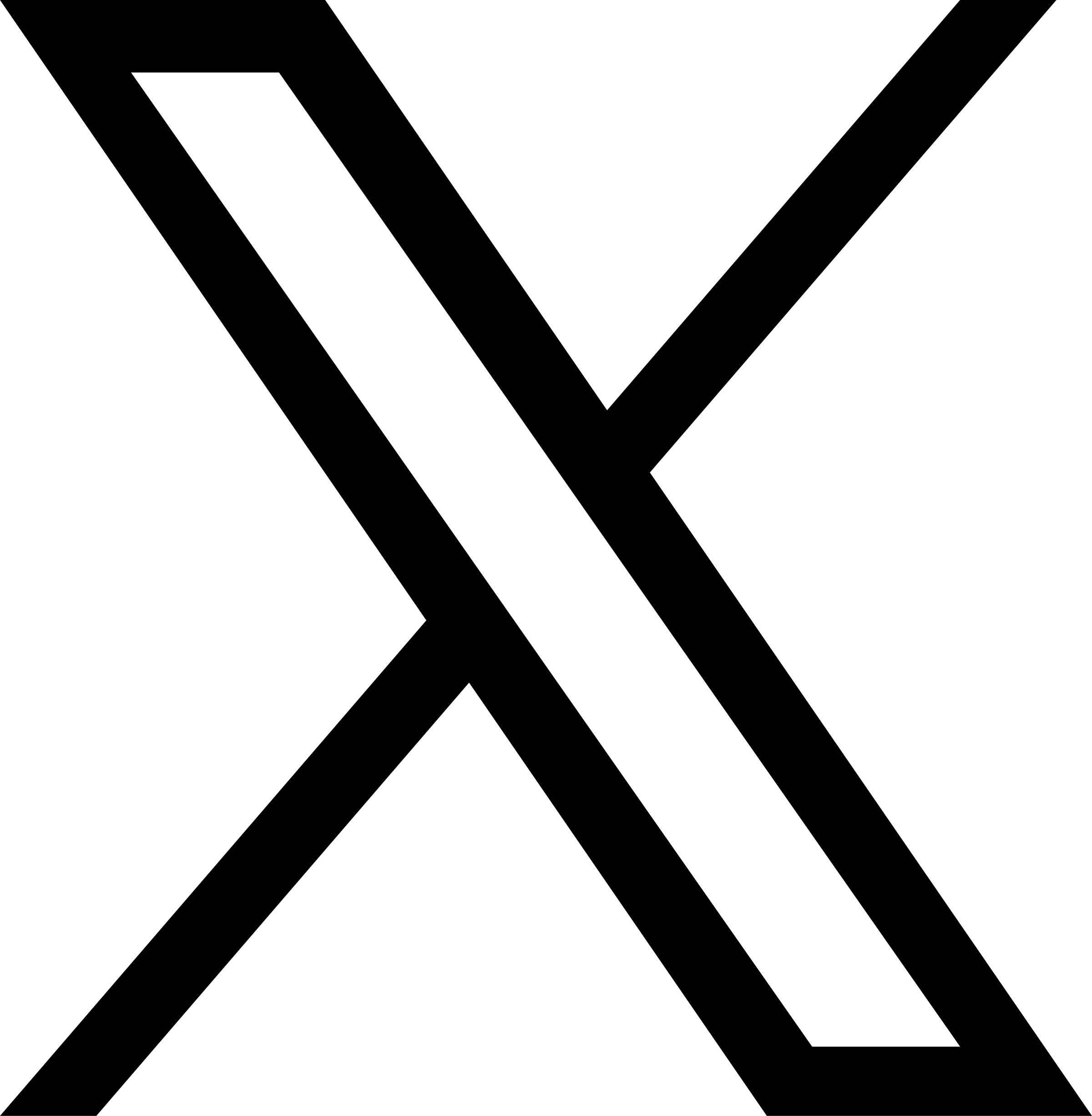狛江市では将来にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の普及を図ると同時に、少子化対策による子育て世帯の負担軽減のため、私立幼稚園等に通っている満3歳から5歳の園児及び一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)を利用する0~2歳の児童の保護者に対し、幼児教育・保育の無償化と合わせて補助金を支給しています。
※保育園等を含む、幼児教育・保育の無償化全般については、「幼児教育・保育の無償化」のページをご覧ください。
※平成27年4月よりスタートした子ども・子育て支援新制度(以下「新制度」という。)移行園については、一部対象外になるものがあります。
(狛江市内に新制度移行園はありません。)
補助金の種類
- 保護者補助金:「私立幼稚園等」に支払った保育料、入園料、その他納付金等に対する補助金です。
- 新入園支度金:「私立幼稚園等」に支払った入園料に対する補助金です。所得制限なく入園時1回限りです(異なる年度に転園し改めて入園料を納めた場合は対象となります )。
- 施設等利用給付:「私立幼稚園」に支払った保育料・入園料に対する給付です。
※新制度に移行した私立幼稚園、認定こども園は保育料が無償化となるため、本給付の対象とはなりません。 - 預かり保育給付・一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)に対する補助:「私立幼稚園等」に支払った預かり保育料または、一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)に対する給付です。利用には保育の必要性の認定申請が必要です(保育の必要性の認定要件)。
- 副食費・教材費の補足給付:「私立幼稚園等」に支払った給食費のうちの副食費や、教材費の実費相当額に対する補助金です。
- 「私立幼稚園」とは、私立の認可幼稚園を指します。
- 「私立幼稚園等」とは、私立の認可幼稚園、幼保連携型または幼稚園型認定こども園、私立の特別支援学校幼稚部、東京都の幼稚園類似の幼児施設、東京都が認定した私立の保育所型または地方裁量型認定こども園を指します。
- 狛江市内にあるのは、私立の認可幼稚園および保育所型認定こども園のみです。
対象者
次の全てに該当する方が対象者となります。
- 園児および保護者の方が狛江市に住民登録があること(園児は必ず、保護者は1人でも可)
※新制度に移行した園に通園する園児については、1号認定を受ける子どものみ対象 - 私立幼稚園等に在園し、入園料・保育料等の利用料を納入していること
- 満3歳児~5歳児を通園させている保護者であること
- 認定を受けていること
支給認定
在籍する施設の種類や、クラス年齢、家庭状況、希望する給付の種類に応じて、複数の認定がありますので、以下の内容を参照し、認定手続きを行ってください。
認定申請のご案内は、原則、入園前に施設からお渡しします。ただし、施設に在庫がない場合がございますので、入園までに案内がない際は、児童育成課へご連絡ください。
認定には、『施設等利用給付認定』と『教育・保育給付認定』の2種類があります。希望する給付制度によっては、『施設等利用給付認定』と『教育・保育給付認定』の両方の認定を受ける必要があります。
施設等利用給付認定
| 認定区分 | 認定条件 | 備考 |
|---|---|---|
| 1号認定 | ・満3歳以上の幼児 (3歳の誕生日の前日以降) |
新制度に移行していない幼稚園の教育時間のみを利用する幼児が受ける認定 |
| 2号認定 | ・3歳児クラス以上の幼児(満3歳以後、初めの4月1日を経過した幼児) ・保育の必要性を満たす |
新制度に移行していない幼稚園の教育時間に加え、預かり保育に対する給付を受けるための認定 |
| 3号認定 | ・満3歳以後(3歳の誕生日の前日以降)初めの3月31日までの幼児 ・保育の必要性を満たす ・個人住民税非課税世帯 |
新制度に移行していない幼稚園の教育時間に加え、預かり保育に対する給付を受けるための認定 |
教育・保育給付認定
| 認定区分 | 認定条件 | 備考 |
| 1号認定 | ・満3歳以上の幼児(3歳の誕生日の前日以降) | 新制度に移行した幼稚園・認定こども園(幼稚園枠)の教育時間のみを利用する幼児が受ける認定 |
| 2号認定 | ・満3歳以上(3歳の誕生日の前日以降) ・保育の必要性を満たす |
満3歳児クラスの間、新制度に移行していない幼稚園・新制度に移行した幼稚園・認定こども園(幼稚園枠)の教育時間に加え、預かり保育に対する給付を受けるための認定(※) |
| 3号認定 | ・満3歳未満 (3歳の誕生日の前々日以前) ・保育の必要性を満たす |
幼稚園型一時預かり事業Ⅱを利用する幼児が給付を受けるための認定(※) |
(※)別紙を参照
保護者補助金・新入園支度金・施設等利用給付
所得に関係なく最低月30,600円が補助されます。令和7年9月以降は、月32,300円が補助されます。
(所得等により上乗せあり。詳細は下表をご覧ください。)
※支給額は保護者が私立幼稚園等に納めた入園料・保育料等の範囲内です。納めた入園料・保育料等の合計が補助限度額を下回る場合は、保護者が納めた額を上限としてして支給します(対象となる入園料・保育料等には受験料・園バス料・給食費・積立金等は含まれません)。
| 階層 | 補助金 | 補助限度額(月額) | |||
| 第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |||
| 第1階層 |
|
施設等利用給付 | 25,700円 | ||
| 保護者補助金 | 9,300円(※11,000円) | ||||
| 第2階層 |
|
施設等利用給付 | 25,700円 | ||
| 保護者補助金 | 6,300円(※8,000円) | 9,300円(※11,000円) | |||
| 第3階層 | 表2に該当する世帯 (世帯年収目安360万円未満) |
施設等利用給付 | 25,700円 | ||
| 保護者補助金 | 4,900円(※6,600円) | 9,300円(※11,000円) | |||
| 第4階層 | 表2に該当する世帯 (世帯年収目安680万円未満) |
施設等利用給付 | 25,700円 | ||
| 保護者補助金 | 4,900円(※6,600円) | 8,700円(※10,400円) | |||
| 第5階層 | 表2に該当する世帯 (世帯年収目安730万円未満) |
施設等利用給付 | 25,700円 | ||
| 保護者補助金 | 4,900円(※6,600円) | 8,100円(※9,800円) | |||
| 第6階層 | 第5階層を超える世帯 (世帯年収目安730万円以上) |
施設等利用給付 | 25,700円 | ||
| 保護者補助金 | 4,900円(※6,600円) | ||||
| 第1階層~第6階層の全ての階層 (所得制限なし) |
新入園支度金 | 年額 30,000円 |
|||
表1の※は、令和7年9月以降の補助限度額を表します。
- 補助限度額は、表2の扶養親族数の内訳、市民税所得割額により決定する階層ごとに、園児が兄・姉から数えて第何子に当たるかで上記の補助限度額が決まります。
- 「ひとり親世帯等」とは、保護者または保護者と生計を一にする世帯に属する者が以下に該当する世帯とします。
- 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない方で現に児童を扶養している方
- 身体障がい者福祉法第15条第4項の規定により身体障がい者手帳の交付を受けた方(在宅の方に限る。)
- 療育手帳制度要綱の規定により療育手帳(東京都の場合は愛の手帳)の交付を受けた方(在宅の方に限る。)
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方(在宅の方に限る。)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の方に限る。)
- 国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金の受給者(在宅の方に限る。)
表2 扶養親族数による市民税所得割限度額表は下記をご参照ください。
表の見方(補助金額の確認)
補助金額は、世帯の市(区町村)民税所得割額(住宅借入金等特別税額控除、配当控除、外国税額控除、寄附金控除等の各種控除適用前(調整控除を除く)の額)に応じて決定します。
※指定都市(近隣では川崎市・横浜市等)で算出された所得割額は、6/8を乗じた額で算出いたします。
- 世帯の当該年度の市(区町村)民税所得割額を確認します(父母の合算。同一世帯に別に家計の主宰者がいる場合はその全ての者の合算)。
所得割額は、一般的に勤務先から6月に渡される、市(区町村)民税・都(道府県)民税額決定通知書で確認できます(自営業者等の方は市(区町村)から6月に送付されます)。なお、算定には上記控除の適用前の額を採用するため、決定通知書の額と異なる場合があります。 - 次に、「表2」の満19歳未満の扶養親族の人数を見て、ご自身の16歳未満、満16歳以上~19歳未満ごとの扶養親族の人数と先に確認した市(区町村)民税所得割額を「表2」の市民税所得割限度額に当てはめ、該当する階層を確認します。
- 最後に「表1」で、お子さんがどの階層の第何子に当たるかを見て、支給される補助金(補助限度額)を確認します。
申請の方法
6月中に私立幼稚園等から申請書とお知らせが配布されますので、必要事項を記入し、私立幼稚園等に提出してください。
転入などにより私立幼稚園等から申請書等が配布されない場合は、児童育成課までお問い合わせください。
※法定代理受領分の給付金・補助金が保育料等から差し引けない場合、償還払い方式で支給するため、すべての方の提出が必要です。
「法定代理受領」とは、狛江市から幼稚園等に対し各園児の給付額を先払いし、幼稚園等が保護者から徴収する利用料から差し引く方法です。
「償還払い」とは、保護者が幼稚園等に利用料を支払い、後から給付を受ける方法です。
※以下に該当する方は、申請書のほかに添付書類が必要です。
(1)令和7年1月1日に狛江市以外に住んでいた方
その住所地の区市町村長が発行した『令和7年度住民税課税(非課税)証明書』(区市町村民税所得割課税額、総所得、控除額、扶養人数等の記載のあるもの、コピー不可)
- 保護者両方の課税(非課税)証明書が必要です。ただし、配偶者控除を受けていることがわかる場合は、控除配偶者の課税(非課税)証明書を省略することができます。
- 園児が同一世帯に属している父母以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の扶養家族となっている場合等は、そのすべての方の課税(非課税)証明書が必要です。
(2)令和7年1月1日に海外に住んでいた方
- 令和6年1月1日~令和6年12月31日の期間の所得を確認するための給与証明等 (※日本語表記以外の場合は、翻訳したもの)
※住民税未申告・添付書類の不足等で税額が判定できない場合、補助金が支給されませんのでご注意ください。また、修正申告をした場合は、児童育成課へご連絡ください。
(3)ひとり親世帯等の方
ひとり親世帯等についての1~7により以下の書類が必要です。
- 1の場合 生活保護を受けていることを証明する書類
- 3の場合 『身体障害者手帳』の氏名が記載されているページの写し
- 4の場合 『療育手帳』の氏名が記載されているページの写し
- 5の場合 『精神障害者保健福祉手帳』の氏名・生年月日・有効期限が記載されているページの写し(令和7年度有効のもの)
- 6の場合 『特別児童扶養手当受給証明書』の写し
- 7の場合 『年金手帳』の写し
※2は書類は不要です。
償還払い方式での支給の時期
- 保護者補助金は、年4回(8月末、10月末、2月末、5月末)の振込予定です。
※4,900円~9,300円の内4,900円超の支給がある場合、4,900円超(令和7年9月以降は、6,600円~11,000円の内6,600円超の支給がある場合、6,600円超)の部分を償還払い方式でお支払いします。
- 新入園支度金は、年4回(8月末、10月末、2月末、5月末)の内、新入園後の直近の支給時期に振込予定です。
年度終了時に、当該年度中にいくらお支払いしたか園を通じてご案内します。
|
対象月 |
支給日(予定) | |
|---|---|---|
| 1回目 | 4~6月分 | 8月末 |
| 2回目 | 7~8月分 | 10月末 |
| 3回目 | 9~12月分 | 2月末 |
| 4回目 | 1~3月分 | 5月末 |
預かり保育補助
対象者
対象となるためには、「保育の必要性を満たす」認定が必要です。
詳しくは、「保育の必要性の認定要件」の項目をご参照ください。
補助上限額
- 「3歳児クラス以上」の「保育の必要性を満たす世帯」
(以上の要件を満たし、施設等利用給付認定の2号を受ける者)
→1日450円かつ月額11,300円 - 「満3歳児クラス」の「保育の必要性を満たす世帯」で「市町村民税非課税世帯」
(以上の要件を満たし、施設等利用給付認定の3号を受ける者)
→1日450円かつ月額16,300円 - 「満3歳児クラス」の「保育の必要性を満たす世帯」で「市町村民税課税世帯」の「第2子以降」
※令和7年9月以降は「第2子以降」を「第1子以降」へ拡大
(以上の要件を満たし、教育・保育給付認定の2号を受ける者)
→1日450円かつ月額16,300円 - 「一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)」を利用し「保育の必要性を満たす」「市町村民税課税世帯」で「0~2歳児」の「第2子以降」
※令和7年9月以降は「第2子以降」を「第1子以降」へ拡大
(以上の要件を満たし、教育・保育給付認定の3号を受ける者)
→月額42,000円
申請の方法
預かり保育の補足給付については、下記の請求書をご利用ください。
償還払い方式での支給の時期
預かり保育の給付補助金は、年2回(12月末、5月末)の振込予定です。
給付方法のご案内は、狛江市から保護者へ直接ご案内いたします。
| 対象月 | 請求書案内予定 | 支給日(予定) | |
|---|---|---|---|
| 1回目 | 4~8月分 | 10月 | 12月末 |
| 2回目 | 9~3月分 | 4月 | 5月末 |
副食費・教材費の補足給付
副食費の補助
「私立幼稚園等」に支払った給食費実費のうち、 おかず・おやつ・牛乳等の副食費の実費相当額に対する補助です。
「市区町村民税所得割額が77,101円未満の世帯」または「世帯内の小学3年生以下の子を数えて第3子以降の幼児」
→月額4,800円
日用品・文房具等の補助
「新制度移行幼稚園または認定こども園に在籍」し、「生活保護法の規定による保護を受けている世帯」
→月額2,500円
副食費・教材費の補足給付については、下記の請求書をご利用ください。
また、償還払い方式での支給の時期については、預かり保育補助と同じスケジュールとなります。
その他
ご不明の点は児童育成課にお問い合わせください。
また、よくある質問については、「幼稚園に関するお問い合わせ」にまとめてありますのでご覧ください。